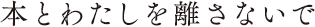category archives : ブログ
2020.10.11
祖父を訪ねて
車があまりにも汚れていたので「洗車したら?」と父に言うと「誰も見てへん。乗れたらええねん」と返ってきた。
数年前に買い換えたというトヨタのヴィッツはフロントガラスも水色のボディも雨水や埃で黒ずんでいた。
父と二人で車に乗るのは何年ぶりだろうか。思い出せない。10年?20年?
ウイルスが他人事ではなくなってきた頃、98歳の祖父がデイサービス先で転んで腰の骨を折って寝たきりになり、数日入院した末に介護付き老人ホームへ移って行った。認知症ではなかったが元々目が悪い上に足元も覚束なくなってきたので転んだことには誰も驚かなった。記憶も曖昧で顔を合わすと「何処に住んどる?子どもの名前は?仕事は何しとる?」と毎回同じことを聞かれる。時々叔父(父の弟)と間違われる。
梅雨が明けた頃に見舞いに行こうとしたが「こういう状況なので予約制になり対面での面会は出来ない」と言われ足が遠のき、何となく夏が終わるのを待ってから予約をしてもらい、実家へ帰った。午前と午後、ひと組ずつしか面会は出来ないらしい。面会と言ってもオンラインで、ただでさえ会話の噛み合わない人と空間を挟んで上手く会話出来るのだろうか。祖父の状況を聞くと「目がほとんど見えなくなっている。食欲はあるし酒も飲むが流石に痩せてきた。でもはっきり喋るけどね」と母は言った。
朝食を済ませ、車に缶チューハイのケースと秋冬用の着替えを積んで父の運転で老人ホームへ向かった。「この街も汚くなってしまった」と父のぼやきを聞いていると10分強で着いた。
エントランスを抜けると左手に受付があって、女性のスタッフが「こんにちは」と元気に出てきた。父は慣れたように「お世話になっております」と荷物を渡し、そのまま広いロビーに向かい腰を下ろした。四人がけの木製のテーブルが三つ並んでいる。僕らの他には誰もいなかった。他のスタッフがどこからか出てきて「準備致します」と軽い足取りで廊下の奥へ消えていった。ロビーは庭に面していて東向きの窓から登り始めた陽の光を吸い込んでいた。窓の向かいには白い本棚がある。中井久夫の本が数冊と司馬遼太郎や津本陽の小説、それとオキーフの自伝が並んでいた。
本を読むでもなく背表紙を撫でていると「お待たせしました」と後ろから声がした。スマホを持ったスタッフが父の元へ歩み寄る。僕はてっきりモニター越しにどこか仕切られた空間で話すと思っていたので面食らった。この広い空間で手のひらに乗った長方形に向かって話すのか。スマホを覗くと鼻にチューブを差した祖父が仰向けに寝転んでいる。目は開いているのか閉じているのかわからない。祖父の傍でスマホを持っているスタッフの手が見え隠れしている。画面が顔に近づいていく。父が「もしもし」と声を上げると「—か?ご苦労さんです」と祖父が答える。僕の来ていることを父が伝えると「元気でやれよ、何処に住んどるんやった?子どもは元気か?仕事は何しよるんや」といつもと同じ会話が始まった。僕がどこで話をしようと祖父にはほとんど関係のないことだった。確かに痩せたように見えたが悲壮感はなかった。もうすぐ100歳なのだ。今更祖父のどんな姿を見てもさほど驚かない。ご飯を食べられて好きな酒を飲めるのだから十分だと思った。
形だけの面会はすぐに終わった。また来るよと通話を切った。いつ逝ってしまうかわからないが、せめてまた手を握れるように願うしかない。それよりも僕は帰り道、フロントガラスの汚れを見たときに父の「乗れたらええねん」という声がこだまして、言いようのない寂しさに襲われた。父は身だしなみに気をつける人だった。派手ではないが傷まない永く着れる上質の服を好んだ。服装や髪型について昔はとやかく言われた。みっともない仕草や装いを嫌った。外見と車のことは別の問題かも知れないが数年前までの父なら車をきちんと洗っていただろう。祖父はもうすぐ100で父は70、僕は40だ。これまで意識をしてこなかった30年の隔たりが僕の人生に影のように気配を消しながらぴったりと付いて来ていたことを知った。そしてその時間の重みやその重みがもたらすものが陽炎のような輪郭を持って目の前に迫って来ることを受け入れるしかなかった。
2020.09.09
blackbird gift cardについて
企画・デザイン:微花
製作:花店note
発売:blackbird books
blackbird booksオリジナルのギフトカードをリリースしました。
以下、製作・発売に至った経緯を簡単にお知らせ致します。
LINEを遡って見ると植物図鑑「微花」を作っている石躍さんと西田さんからbbbの図書カードを作りたい、と最初に連絡が来たのは2020年の4月13日。
この日は、新型コロナウイルス感染症の影響であらゆる業態の店が「開ける・閉める」の選択を迫られ、「テイクアウト・通販」の準備に右往左往する中、bbbとしては本を必要だと言う人たちのために、そして家族を養うために夕方まで店を開けるという選択をしてしばらくしてからのことでした。
お世話になって来た多くの本屋の苦しい現状を見ていて、何か出来ることはないかと連絡をくれたのです。
blackbird booksという場を続けて欲しい、知って欲しい、今は行けなくともいつか訪れて欲しい、という明確でこちらが少し遠慮してしまいそうなメッセージを受け取りました。
以前にもどこかで書きましたが「微花」の二人とは店を創業した頃からの付き合いなので6年ぐらいになります。取引先の相手として、店と客の関係として、そして今では友人として気の許せる付き合いがあります。
僕らの間には本と花があり、本屋という場所がありました。本屋以外の場所で言葉を交わすことは打ち上げなどの年に一、二回の例外を除いてありません。
本屋という小さな空間で交された短い時間の積み重ねだけで信頼関係が生まれていることに、小さな感動を覚えます。
bbbでギフトカードを作るのであれば、やはり「花」を使いたい、ということでした。
bbbは花屋を併設しているので花を担当している妻に早速相談すると彼女は是非やりたいとのことでした。
今回のギフトカードには彼女の運営する花店noteの押し花を使っています。
僕もこの数年実際に横で見ていてはっきりと分かったのですが生花を販売すると、どうしてもロスが出ます。
枯れる前にドライフラワーにすることは出来ますが、全ての植物を出来るわけではないし、切り落とすものも出て来ます。枯れたと一口に言っても枯れた花の美しさもある。
それらを箒で片付けることは簡単ですが、妻はそうすることを嫌っていました。
一方で「微花」は道端の植物を観察し、雑草という名の花はないという信念があり、名前の忘れられている花や見過ごされる風景(一歩外に出れば、気づかないだけで視界には植物が溢れているはずです)、つまり小さな生命の呼吸のようなものを汲み取っていました。
妻と微花の間には共振するものがあります。
blackbird gift cardはその小さな共感の振動、そして小さな生命の残響、そういうものが形になったと思います。
最初は感染症の影響もあり、営業が苦しくなる前に、GW明けには出したいね、と話していたのですがアイデアを共有していく中でせっかくなのだから妥協せず、急がず、良い物を作りたいという全員の想いが強くなり、この9月に発表することになりました。
このカードは店頭でのご利用となります。
bbbを紹介したい方、いつか自分で行ってみたい方、本はやはり手に取って選びたい方、コロナをはじめ様々な事情で今は来られることが出来ない方、
贈り物としても、あるいは自分のためにも花を眺めながらどんな本を選ぼうか空想をお楽しみください。
店頭、ホームページで販売致します。

2020.06.12
六年目の出来事
四人は、イシハラという人以外は、酒ではなくウーロン茶やポカリスエットを飲みながら、何も話さずにソファにただ座っている。煙草を吸うわけでもないし、音楽を聴くわけでもないし、テレビや雑誌を見ているわけでもない。世間の常識からすると、決して楽しそうに見えない。だがこれもタテノという人に教えてもらったのだが、楽しいというのは仲間と大騒ぎしたり冗談を言い合ったりすることではないらしい。大切だと思える人と、ただ時間をともに過ごすことなのだそうだ。(半島を出よ / 村上龍)
先日、友人夫婦の営む洋菓子店が閉店した。
本を引き取って欲しいと言われお店を訪ねた時に店を閉めることを告げられた。
全く予期せぬことだったので僕は不意打ちを食らって言葉を失い、しばらく動けなかった。
業種は違うけれど僕らはちょうど同じ頃に店を始めて、同い年ということもあって、親近感があった。
店の佇まい、ふたりが選択している物事、会話から、ふたりが大切にしていることが、僕と共通するものがあった。
僕はふたりのことが好きだった。
お店は物凄く流行っていた。会う度に忙しさは増しているようだった。お菓子も珈琲も本当に美味しかったから。
忙しい、というのは心を亡くす、と書くけれどそこまでとは思っていなかった。
普通の生活が出来なくなってしまったと言っていた。コロナで考える時間が出来たということだ。
客がいくら入っても、睡眠時間が削れたり、無茶な問い合わせを受けたり品のない行為を店でされ「消費されている」と感じれば、店の運営には困難が生じる。
僕もドリンクを片手に店に入って来られたり、意味もなく片手でページをパラパラとされれば意気消沈する。
ただ、お店のことはふたりにしか分からないし、ふたりの間のこともふたりにしか分からない。
僕がふたりに言えたことはウチは続けるからいつでも来てよ、連絡してよ、ということぐらいだった。
後日、兄弟みたいに思っていたから告げるのは辛かったと言われた。
僕は嬉しさと悲しさ、そして悔しさで混乱し、今もまだ糸が絡まったように心の整理が出来ていない。
ふたりのお店がそこにあるというだけで、僕は励まされていた。
2020.04.12
コロナ禍と安倍政権下のbbb、そして言葉について
コロナと安倍政権に追い詰められる中でこの二ヶ月ほど同じことをぐるぐると考えている。
結論がなく、まとまりそうもないので、考えていることをそのまま書く。
大きく分けると二つのことを考えている。自分に向かって問いかけている。
一つは店を開けるべきか閉めるべきか。
bbbでは今のところ営業を続けている。
コロナの影響は長引くだろうから細々とでも続けられる形態を探したい、一度閉めると再び開けるのは難しくなるのではないか、と小さな理由付けみたいなのは幾つもある。
けれど大きな理由はただひとつ、閉めれば収入が途絶えるから。
小三(になった)の長女ともうすぐ一歳の次女がいる。
妻は次女の出産のため昨年会社を辞め、この春からこれまで不定期でbbbで活動していた花屋の活動を始めるつもりだったが長女の学校が休校になったので身動きが取れず、
また次女は4月から保育所が決まったけれど、家に長女はいるし、この状況で預けるのはほとんど意味がないのでそれも延期した。
我が家の収入は本を売るしかない。
つまり、開けるべきか閉めるべきかは死活問題だ。ぎりぎりまで、極限まで、考えている。今も。
二つ目は仕事について。
僕の仕事は何だろうと考える。買い取った本、出版社や個人が作った本を読者に届けること。
簡単ではないが、極めてシンプルな仕事だと思う。
僕は僕のやるべきこと、出来ることをやっていきたい。
本を待っている人がいる。
そして、本を心の拠り所にしている人がいる。本屋に行くことで心の平穏を保っている人がいる。
僕は一人で本屋をしているのでお客さんとは一対一の関係だ。
暮らしていくために、夜を乗り越えるために、本が必要だという個人を僕は具体的に顔を思い浮かべることが出来る。
この人たちがもし、今、本を必要としているのなら、店を開ける理由になるだろう。ならないだろうか。
そして大事なのは、この人たちがいなければ、僕は本屋を続けることが出来ない。ここには相関関係がある。
毎月山のように本を買うあの人、二時間も三時間も粘って文庫本を一冊震える手で買うあの人。
ただ奇跡的に政府が方向転換したり政権交代があったりして収入の不安が一時的にでも解消された場合、僕は店を閉めるだろう。
感染のリスクを減らすことは僕にとっても家族にとっても社会にとっても大切なのは分かっている。
そしてそうなった時、相関関係は崩れるだろうか。僕は、これが僕の仕事だと、見栄を切っていただけだろうか。
結局のところ、社会が、政治によって決められている(歪められている)以上、僕は信頼出来る政府、あるいはリーダーの「言葉」を望んでいるのかも知れない。
「お金のことは心配しなくて良い。預かった税金でみなさんの健康で文化的な最低限度の生活を保証する。本を必要な人が困らないような社会をつくる。だから、blackbird booksも協力して欲しい」
その言葉を信用出来る人間から放たれるのを半ば諦めながら待っている。
そしてまた同じ問いを繰り返している。
2019.10.08
岡野大嗣さんのこと
岡野さんにはblackbird booksがまだ小さなマンションの一室で週末だけ営業していた頃に出会った。
どうやって彼がお店のことを知ってくれたのかは分からない。
何を話したのかは覚えていないし、彼が何の本を買ったのかも思い出せない。
ただレジで会計を済ませると、彼は(今となってはいつものように)少し俯いて、眼鏡の奥から上目遣いでこちらを見て、
「短歌を書いているんです、良かったら読んでみて下さい」と恥ずかしそうに言って『サイレンと犀』を手渡されたのを覚えている。
僕はその頃短歌には全くの無知だったけれど、『サイレンと犀』を瞬時に『silent sigh』に変換して、この人は音楽が好きで僕と同年代なんだなと思った。
『silent sigh』は僕らが出会う10年ほど前にbadly drawn boyが出したシングルで僕は7インチを買ってしまうほどに聞き込んだ大好きな曲だった。(ヒュー・グラントが主演した「about a boy」の主題歌。何と言っても原作がニック・ホーンビィだ)
その本を手にした時には僕にとって彼はもう全く過去のアーティストになっていたけれど、懐かしいメロディーやセンチメンタルな歌詞を思い出して少し嬉しくなった。
そういうことがあってその歌集と岡野さんことは強く印象に残った。
岡野さんはそれから定期的にお店に足を運んでくれていて、お店でも短歌を少し置くようになったり、別の本でイベントに出て頂いたりと交流が今に至るまで続いている。
岡野さんの短歌やTwitterでの呟きを見て驚かされるのは幼稚とも取られかねない生命と風景への純粋な眼差しだ。
河川敷が朝にまみれてその朝が電車の中の僕にまで来る
ハミングのあれはユーミン お米研ぐ母に西日は深くとどいて
完全にとまったはずの地下鉄がちょっと動いてみんなよろける
もう声は思い出せない でも確か 誕生日たしか昨日だったね
うらがわのかなしみなんて知る由もないコインでも月でもないし
生きるべき命がそこにあることを示して浮かぶ夜光腕章
微笑ましい記憶やユーモアに繋がる一瞬の光景、生と死の間に横たわる疑問への純白な問い、それらを31文字で拾い集める。
彼は手のひらからこぼれ落ちる僅かな光も見落とさないように、無くさないように歩いているように見える。
お互いもう40になるけれどどうしてそんな眼差しを持ち続けることが出来るのだろう?
佐野元春の言葉を借りれば「ステキなことは ステキだと無邪気に笑える心」。
岡野さんはそういう心を持っていて、僕はそこに惹かれている。
copyright © blackbird books all rights reserveds.