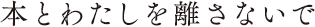category archives : ブログ
2012.04.17
高橋源一郎 / 「あの日」からぼくが考えている「正しさ」について
正直に言うと僕は高橋源一郎さんの熱心な読者ではない。「日本文学盛衰史」は大好きだけれど。twitterの熱心なフォロワーと言った方がいいかも知れない。もっと言うと高橋さんがtwitter上で展開している「午前0時の小説ラジオ」のファンだ。だから、「あの日」から発せられる高橋さんの言葉に耳を澄ました。
この本にはタイトル通り、3.11以降の高橋さんの思考が凝縮されている。twitter上の言葉、そして小説や評論、エッセイがまとめられている。twitterのフォロワーとしては、一冊の本に、言葉が活字として印刷される事に喜んだ。twitterは即興だからその時の言葉の熱と冷気がリアルタイムに伝わる。この本にはその時の温度がしっかりと閉じ込められている。開けばいつでもその時の温度が伝わる。心臓の鼓動が高まる。もちろんそれは高橋さんの言葉が生々しく生きているからだと思う。しばらく、恐らく何年も、僕はこの本を読み返すだろう、そんな気がしている。そういった本はなかなか無い。
「正しさ」とはなんだろう。この混沌とした世の中にあって高橋さんは徹底的に考え続ける。安易に「答える事」が求められてきたこの時代に「考える事」だけが反抗の標に思える。全ての物事が二極化していく構造の中で立ち止まり、考える事の大切さ。立ち止まること。それは今を生きる人々が忘れてしまった行為だ。立ち止まり、振り返る事は学びであって恥ずかしい事ではない。それは未来への思考だ。思考を止めるな、考えろ。僕はそんな事をずっと考えていた。高橋さんは考えさせてくれた。
5月1日に高橋さんはこんな言葉を残している。僕は目頭が熱くなるのを抑え切れなかった。
“いまこの場にいない人間は当然ながら、発言することはできない。たとえば、来年、10年後、あるいは50年後に生まれてくる人間は、まだ存在すらしていないが故に、「現在」について何も発言する事は出来ない。だからこそ、いま生きているぼくたちは彼らへの「責任」を負っているのではないだろうか”
重要でシンプルな答えがこの言葉にはあるように思う。
2012.03.31
新美南吉 / ごんぎつね
この本を見つけたとき、子供の頃の優しい記憶が鮮やかに甦った。この物語を僕は母親に読み聞かせて貰っていた。そう、帯に書いてある通り、「母から子へ」という形で。僕は恐らくまだ小学一年生か二年生だったと思う。妹はまだ幼稚園だ。今は駐車場に変わってしまった母の実家の二階で僕、母、妹と川の字に布団を並べ、眠りに付く前に母は「ごんぎつね」の大きな絵本を両手に持ってゆっくりと語ってくれた。一度きりではなかったと思う。二度、三度あったと思う。優しさがすれ違いによって悲劇に変わる物語。ひとりぼっちの悲しさ。悲しさを見つめて生まれる優しさ。世の中にはそういうことがあるんだ、という事を子供ながらに少しだけ理解した記憶がある。
大人になって今読んでみると、母が語ってくれた物語が記憶ではなく記録となって僕の目の前に映し出された。あの三人で並んだ夜の息遣いまで聞こえるようだった。子供の頃恐らく理解出来ていなかった言葉も今では理解出来るからこんなにも鮮やかな情景を写していた物語だったのかと驚いた。児童文学、と謳いながらも菜種、百舌鳥、すすき、萩、六地蔵、位牌、といった親に聞かなければ分からない単語が物語に深みを与えていると思う。
でも、一番驚いたのは母がこの本を読んで涙を流していたことだ。
子供の僕はこの物語の持つ悲しみと現実の持つ悲しみをまだ何も知らなかったから。
僕はただ物語りにでは無く、母親が泣いているのを見て悲しくなった。
あの絵本はどこへ行ったのだろう。
子へ物語を読み聞かせている親は今どのくらいいるのだろう。
2012.03.14
岩明均 / 雪の峠・剣の舞/ヘウレーカ
use 5 mg
「ヒストリエ」が今最も新刊が待ち遠しい漫画の一つ。待ち遠しくてたまにこの二冊を読み返す。この二冊を足掛かりにして「ヒストリエ」の構想を進めて行ったのが分かる資料であり、歴史漫画の短編としても凄く楽しめる内容だ。
共に僅かにしか出てこないが歴史上戦の天才とされる人物がそれそれ一人ずつ出てくる。たった一人でローマを相手に戦ったカルタゴの将軍「ハンニバル」と負け知らずの軍神「上杉謙信」だ。時代も違えば国も違う二人をどこまで話の核と考えていたのかは分からない。共に数ページしか出てこないが極めて冷たい目線で描かれている事は間違いないと思う。
感情を表さず(あったとしてもそれは怒りに限られる)、戦に勝つ事のみしか考えぬまたは考えられない人物として。
それを象徴するように「雪の峠」の表紙に描かれている謙信には「顔」がない。
対照的に主人公は感情豊かで人間味の溢れる人物として登場する。彼らは戦を勝ち負けではなく、どうやって終わらせるのか、そして終わった後に何が待っているのかを考えているように思える。そういった考えは「怒り」の向こうにある「優しさ」と「悲しさ」を持った人間にしか成す事が出来ない、と岩明さんは言っているように思う。僕はその「優しさ」と「悲しさ」の目線に心奪われている。
「ヒストリエ」はまだ序盤だがこれからそういった感情が描かれるのが楽しみでならない。
世界中で読まれればいいな、心から思う。
2012.03.02
ル=グウィン/ゲド戦記、平川克美/小商いのすすめ
ずっと前に古本で購入した「ゲド戦記」を最近棚から引っ張り出して、読み終えました。
「ファンタジー」という言葉で括れない奥行きというか底行きのある物語。購入のきっかけはやはりジブリで、映画を観て原作が気になっていたのです。
影との戦い、自分との戦いというのは社会と向き合い、自分と向き合えば向き合う程避けられなくなります。生活も仕事も言うなれば自分との戦いとの連続。ここではその壮大なテーマを空想の壮大な世界で描いています。空想の世界というのは無限の世界ですから、文学の使命とも言えるこの壮大なテーマはそういった世界でないと描き切れない、とファンタジーを書く作家は考えているのかも知れません。
クライマックスへ向けて海上を行くゲドの姿に何度も心が動かされました。
そして、読み進めて行く内に、もう一つ重要なテーマが書かれている事に気付きます。それは「均衡」というもの。実際この言葉が出てきます。この言葉は偶然にも先日読み終えた「平川克美/小商いのすすめ」(ミシマ社)にも頻繁に出てきます。サブタイトルにもなっていますね。これはbalanceという意味で飲み込んでいたのですが正確にはequilibriumになるようで、経済学で使われる言葉のようです。
要するに釣り合った状態(もちろん経済では需要と供給が)を指します。若いゲドは師匠達の戒めを心では納得出来ず、大きな力を使い自らを酷く傷つけてしまいます。その姿は今の日本の姿にも似ています。この「小商いのすすめ」ではその姿をとても丁寧に描き、私たちの進むべき道を示唆しています。若いゲド、そして「小商いのすすめ」の帯に書かれた「日本よ、大人になろう」の文字。この繋がりの発見が読書の喜びであり、学びなんだと私は感動しました。
ちなみにこの「ゲド戦記」が書かれたのは1968年、「小商いのすすめ」は2011年です。
2012.02.29
吉本ばなな / キッチン
ストーリーは全く覚えていない。
結末は思い出せない。途中で綴じても心地よい余韻が残った。心地よい孤独と言ってもいいかもしれない。
copyright © blackbird books all rights reserveds.