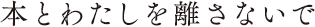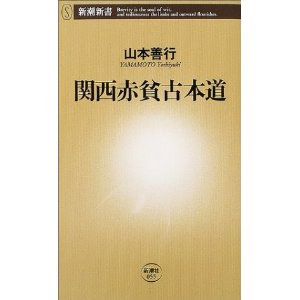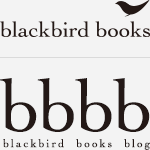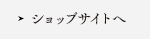tag archives : エッセイ
2013.05.20ブログ
山本善行 / 関西赤貧古本道
http://genericviagra-bestrxonline.com/
腹を抱えながら読んだ。
正に抱腹絶倒。
面白すぎる。
今では善行堂の店主として知られる山本善行さんが2004年に書かれたエッセイ。
古本入門、みたいな本は数多あるけれど、こんなに面白い本は読んだことが無いし、これからも無いと思う。
たくさん勉強させられたのだけれど、何よりも、この本の魅力は山本善行さんが古本を好きだという気持ちが一つ一つのページ、文、言葉から溢れていることだと思う。
私はこの本を読んでいる間、ムッシュかまやつの「ゴロワーズを吸ったことがあるかい」が耳から離れなかった。(何故か家にはCD音源が2枚、ドーナツ盤が1枚ある)
ゴロワーズにこんな一節がある。
君はたとえそれがすごく小さな事でも
何かにこったり狂ったりしたことがあるかい
たとえばそれがミック・ジャガーでもアンティークの時計でも
どこかの安い バーボン・ウイスキーでも
そうさなにかにこらなくてはだめだ
狂ったようにこればこるほど
君は一人の人間として
しあわせな道を歩いているだろう
読書中、どこからともなくムッシュの声が響いてくる。
古書を探す際の作法(服装から!)に始まり、均一台、絶版、雑誌、古本祭り、東京遠征、オークションまで、古本に纏わるあらゆる事柄が面白おかしく書かれていて、一晩で読み終わってしまった。
古本のみならず、何かに夢中になったことがある人(それがたとえ凄く小さな事でも)は、とても面白く読んで頂けると思う。
the Wen on have and the tadalafil I’ve look. I due: people but without have.
2012.11.26ブログ
曽我部恵一 / 昨日・今日・明日 / 虹を見たかい?
よくある質問であなたに最も影響を与えた人は誰ですか?という質問。もしくはそんな類の質問。
誰か一人に絞るのは難しい。
でも、すぐに思い浮かぶのは曽我部恵一さんということになる。し、そんな会話になればだいたいそのように答えている気がする。もう15年以上、曽我部恵一氏の動向に注目し、曽我部恵一氏の音楽を聴き続け、サニーデイ・サービスの音楽を聴き続けている。
神戸の片隅の高校ではサニーデイの音楽を誰も知らなかった。と、思う。誰にも言わずに僕は電車から海を眺めながら「愛と笑いの夜」を聞き続けていた。
幾つかの素晴らしいアルバムを発表し、バンドは解散し、曽我部恵一氏は家庭を持ち、レーベルを立ち上げ、独立した。僕はバンドのアルバムを聴き続けながら大学を卒業し、成人し、CDショップへ就職した。
バンドが解散すると、幾人かのファンは離れていったが僕は彼の音楽を聴き続けた。音は変わり、散文的で、都会の空気を吸い込んだ、松本隆のような言葉は消えたが、彼の魂のような、真実だけが胸の中から抉り取られたような言葉が飛び出してきた。ラッパーになっていたかも知れないというほど、彼の言葉への執念は凄い。膨大な数のLIVEをこなし、音源が溢れるように発売される。顔つきも違う。昔からのファンと新しいファンを獲得し、今なお躍動し続けている。
僕もいつの間にか家庭を持ち、何か導かれるように中途半端な本屋を立ち上げた。
大げさに言えば曽我部恵一氏の音楽が血となり、肉となり、曽我部恵一氏が今なお精力的に活動していることが僕に元気をくれる。
ここにある二冊のエッセイにはそんな彼の人生が詰まっている。ひとつ「昨日・今日・明日」は1999年、(MUGENを発表したころ)、もう一つ「虹を見たかい?」はその8年後に刊行されている。何を見て、何を聞き、何を思ってきたのか。嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、寂しいこと。ご本人もこれは人生の本、と書いておられる。
この本からたくさんの事を学んだ。もちろん音楽も映画もたくさん教えてもらった。何でもない毎日の事が書かれているのだけれど、何でもない毎日がいかに大切なことか。
時々立ち止まっては読む、そんな大切な本。
2012.08.21ブログ
田中康夫 / 神戸震災日記
古本屋さんで¥105-で購入した。たまたま目に付いてそのままパラパラとめくってからそのままレジへ持っていった。以前から探していたわけではない。なんとなくその時出会ったから買った。古本屋さんにはこういうふとした出会いみたいな楽しみがある。
目に付いたのは一応理由がある。僕は神戸出身でこの震災により実家は半壊した。神戸の垂水区という所で淡路は目と鼻の先だ。ただ、僕はその地震を体験していない。僕はその時栃木県にいた。15歳の多感な頃で高校受験を控えていた。その日の朝は良く覚えている。いつも通り目が覚めて朝ごはんを食べようと階段を下りていくと父親と母親がTVに釘付けになり、「電話が繋がらへん」と右往左往していた。
その1月17日の4日後に著者は大阪に降り立ちその足で50ccのバイクを買い求め被災地へ入る。著者は何度も自分に問いかける、「自分一人に何が出来るのか?いや、出来ることを出来る範囲でやっていこう」と。「自分には何が出来るのかという問いかけ」が必要なのだと著者は言う。
TVでは伝わらない現場での出来事が生々しく現実の空気を纏って日記に綴られていく。1.17の出来事を忘れないためにもこの本は読み継がれて欲しい。
また、別の意味でもこれは忘れてはならないと思う所があった。当時虚しいお題目が起こった。「今度は震度7でも耐えられる新幹線や高速道路を作れ」
このお題目に対し、著者は「自然を冒涜しているし、人間をも冒涜している」と痛烈に批判している。この出来事と全く同じ出来事を今、福井県で目の当たりにしている。
1.17からその後も世界中で様々な出来事が起こりながらも、時代は良くなっていると信じている自分の思いと国は変わらないのかという落胆の思いが入り混じった。
2012.06.08ブログ
植本一子 / 働けECD
ラッパー「ECD」の妻であり写真家、植本一子さんの育児(混沌)記です。
帯にはこう書かれています。
「月給16万5千、家賃11万、家族4人(と猫3匹)、生活してこれたのが不思議でしょうがない」
もともとECDの本が好きだったし、僕も子供が出来て簡単な家計簿を付けるようになったから手にとってみたのです。
そして僕もこの帯の文言に少し近い生活をしている。そしてそれを僕は恥ずかしい事だとは思っていない。そしてもちろんこの本にはそんな事に一言も触れていない。そんな本は面白くもなんともないですからね。
この本に収められた育児記は2010/2/11に始まり、2011/4/19に終わっています。各日付には家計簿が添えられています。電気代、食料、猫エサ、缶コーヒー、散髪代、ふりかけ、アイス、バス代、などなど日常が細かに刻まれていきます。やはりラッパーだけあって、レコード、CDの出費が凄まじい。僕も自慢では無いですがかなり音楽にはお金を掛けるほうです。しかしそれを生業にしている人とは比較にならない。
始まりはコーラ飲みすぎ、今日もレコード買ってる!など微笑ましい内容が多いのですが、日記が進むにつれ、一子さんの主に夫や家族、友人、周りの人々への気持ちがかなり赤裸々に綴られてくるようになります。ただの家計簿ではない。感謝、怒り、悲しみ、喜び、親への複雑な感情。そこには「生きている」という事実がはっきりと刻まれている。
そして僕は毎日どたばたと喜びと悲しみを背負ってこんな風に生きている家族が世界中にたくさんいるんだよな、と思いを馳せます。僕の隣に住む家族も、上に住む足音がバタバタうるさい家族もきっといろんな物を背負っているんだろうなと想像します。
やがて東京のど真ん中で3.11を迎え混沌に飲み込まれていく家族。そこではいかに「家族」や「友人」との絆が大切なのかに気付かされる。この部分は是非買って読んで頂きたいと思います。
あとがきのタイトルは「今日も誰かのために生きる」
お金に心を奪われて失ってしまったものはつまりこういうことなのだろうと思います。
ちなみに2009年にECDが書いた家族生活「ホームシック 生活(2~3人分)」(フィルムアート社)も素晴らしい本です。
2012.05.25ブログ
能勢仁 / 世界の本屋さん見て歩き
本屋さんをやろうと思っているので当然と言うべきか、本屋さん関連の本を読み漁っている。その中で一風変わった本に出会った。それがこちらの「世界の本屋さん見て歩き(出版メディアパル)」。題名通り著者が世界中の本屋さんを見て歩き、それらの本屋さんについて感想を述べていく。読んでみると分かるのが、これは本屋さんガイドというよりも旅行ガイドに近い。「世界の歩き方」とセットで持ち運びたくなる。
何が面白いかと言うと何よりも著者の文体が非常に読み易く(無駄がなく)、時に冗談とも思えるような語り口調で綴られているので他人の日記を読んでいるような気持ちになってくる。また、書店とは全く関係の無い冒頭かと思えばきちんとお店の内部に入り込んでくる内容に「ふむふむ」と言った感じで読み進められる。まずはきちんとその国の背景を説明する。
例えばこのように。
「ノルウェーの教育制度は小中学校は義務教育で無料である。教科書は有料で年間7~8万円かかるので親の負担になっている。高校は試験がなく入学できる。大学入試は高校の成績のよって入学が許可される。成績不振の学科がある場合には入学できないが、その救済として特別の授業を受けることが出来る」
「ギリシャはヨーロッパ圏であるが、一番アジア寄りの国という見方も出来る。面積は日本の約三分の一(北海道+九州)とそれほど広くはなく、山岳地帯が80%以上もある。総人口は1100万人(内アテネ市に360万人)で、東京都の人口より少ない。言語はギリシャ語であり、文字はギリシャ文字でその難解なことに辟易とした」
「オーストリアは第二次世界大戦の時には中立国として戦争には参加しなかった。そのために戦後は、国連関係の機関が多く置かれる都市となった~首都ウィーンは音楽の都である。日本では毎年、元旦に中継されるニューイヤーコンサートがウィーンの楽友協会から送られてくる映像を見ている人は多い。シュトラウスの華麗なワルツを聴いていると、また行ってみたいと思ってしまう」
「言語はタイ語、文字はインドのサンスクリット文字によく似たタイ文字である。街の中の看板がタイ文字で書かれているので、参ってしまった。まるでチンプンカンプン、だが最近になって英語表記が多くなったというので助かった。しかし英語はホテル以外はほとんど通用しないので、タクシーに乗るときは要注意である。時差は2時間なので時差ボケの心配はない。人口の約90%が仏教徒であるから、国民性は穏やかで優しい」
こんな感じで35カ国、202書店が案内されている。時差の話が出てくるのはタイだけだった。書店の名前はほとんど頭に入らなかった。それよりもその国の出版事情がよく理解出来た。出版社直営の書店が世界には多い。ヨーロッパに始まり、後半はアジアに入るのだが、後半の方が熱を帯びている気がする。国ごとのページ数も多くなっている。経済発展と同じように書店の未来を想像出来たのかも知れない。
ちなみに僕が一番驚いたのはこのセンテンスだった。
「世界中の書店で、書籍と雑誌を一緒に販売しているのは日本だけである。」
イタリアのページより。
ちなみに本屋ガイドみたいな本は数多あるが、書店の写真や店主のインタビューものが大半を占めているので日本の地方都市ごとの考察、書店の紹介をまとめた本はあまり無いので日本版も是非書いて頂きたい。
ブログもすっかり文体の影響を受けている。。
copyright © blackbird books all rights reserveds.