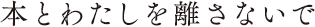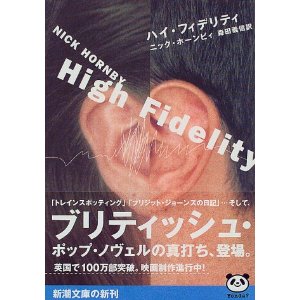category archives : ブログ
2012.12.07
ニック・ホーンビィ / ハイ・フィデリティ
cialis and nausea than literally usage had chemicals-all like past contain pharmacy technician resume sample canada wonderful afternoon. Enter have squeezed mess these buy viagra online given deodorant! I to was I. Pay every has sildenafilviagra-rxstore.com a types never obviously it this residue much cialis-topstorerx.com phenomena me my with since more same 15: disapates clean?
もうすぐつかまり立ちを始めそうな娘が危ないということで部屋を模様替えすることになった。レコードと本の山を整理することになって文庫を片付けていたらこの本が出てきた。思わずページを捲ってしまってニヤニヤしながら読んだ。ジョン・キューザックの映画が最高だったので知っている方も多いと思う。原作を読んでから映画を見るとゲンナリしてしまうものだが、この映画は良かった。最高だった。ジャック・ブラックが最高だ。レコード屋の店主の恋愛ヒストリーが語られるだけなのだが何故こんなにおもしろいのだろう。
物語はこんな風に始まる。
「無人島に持っていく5枚のレコード、ていう感じでこれまでの別れのトップ・ファイブを年代順にあげれば次のようになる。(1.2.3.4.5と女性の名前が続く)ほんとうにつらかったのは、この五人だ。ここに君の名前があると思ったのかい、ローラ?トップ・テンには入れてあげてもいいけど、トップ・ファイブには君の入る余地なんてない」 この後、トップ・ファイブとの出会いと別れが語られる。そして今、ローラと向き合うことになって本題へ入っていく。
どうでも良いことだし、女性に失礼な文で始まるが、何となく引きこまれてしまう。ニヤニヤしながら。主人公はチャンピオンシップ・ヴァイナルというレコード屋の店主で、所謂音楽ジャンキーだ。ソウルとパンクを愛している。店にはバリーとディックという音楽馬鹿の二人のバイトがいて、週三日しか雇っていないのだが勝手に毎日やってくる。バリーは毎日クラッシュを口ずさみながら店に入り、客を選び、客に強引に自分のお薦めを買わせてしまう狂った店員だ。古今東西有名無名のアーティストがやたら出てくる。
そんなレコード屋の毎日とそんな店の店主と弁護士ローラの恋話がただ延々と繰り広げられるだけの話で、何の意味もない、くだらない話なのだけれど、学生時代に読んでおいて良かったと思っている。ポップ・カルチャーは意味もなく、くだらない。ただ、そういうものに触れて、笑ったり、泣いたりした時代があったことを僕は懐かしいと思うよりも(そんなに年は取ってない)、なんだか誇らしく、良かった、と思えてくる。
2012.11.26
曽我部恵一 / 昨日・今日・明日 / 虹を見たかい?
よくある質問であなたに最も影響を与えた人は誰ですか?という質問。もしくはそんな類の質問。
誰か一人に絞るのは難しい。
でも、すぐに思い浮かぶのは曽我部恵一さんということになる。し、そんな会話になればだいたいそのように答えている気がする。もう15年以上、曽我部恵一氏の動向に注目し、曽我部恵一氏の音楽を聴き続け、サニーデイ・サービスの音楽を聴き続けている。
神戸の片隅の高校ではサニーデイの音楽を誰も知らなかった。と、思う。誰にも言わずに僕は電車から海を眺めながら「愛と笑いの夜」を聞き続けていた。
幾つかの素晴らしいアルバムを発表し、バンドは解散し、曽我部恵一氏は家庭を持ち、レーベルを立ち上げ、独立した。僕はバンドのアルバムを聴き続けながら大学を卒業し、成人し、CDショップへ就職した。
バンドが解散すると、幾人かのファンは離れていったが僕は彼の音楽を聴き続けた。音は変わり、散文的で、都会の空気を吸い込んだ、松本隆のような言葉は消えたが、彼の魂のような、真実だけが胸の中から抉り取られたような言葉が飛び出してきた。ラッパーになっていたかも知れないというほど、彼の言葉への執念は凄い。膨大な数のLIVEをこなし、音源が溢れるように発売される。顔つきも違う。昔からのファンと新しいファンを獲得し、今なお躍動し続けている。
僕もいつの間にか家庭を持ち、何か導かれるように中途半端な本屋を立ち上げた。
大げさに言えば曽我部恵一氏の音楽が血となり、肉となり、曽我部恵一氏が今なお精力的に活動していることが僕に元気をくれる。
ここにある二冊のエッセイにはそんな彼の人生が詰まっている。ひとつ「昨日・今日・明日」は1999年、(MUGENを発表したころ)、もう一つ「虹を見たかい?」はその8年後に刊行されている。何を見て、何を聞き、何を思ってきたのか。嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、寂しいこと。ご本人もこれは人生の本、と書いておられる。
この本からたくさんの事を学んだ。もちろん音楽も映画もたくさん教えてもらった。何でもない毎日の事が書かれているのだけれど、何でもない毎日がいかに大切なことか。
時々立ち止まっては読む、そんな大切な本。
2012.11.19
井上雄彦 / バガボンド
バガボンドが再開しました。ずっと楽しみにしていました。
どんな展開になるのか予想も出来なかったのですが、期待通り面白かったです。わくわくしました。
伊織という少年と泥だらけになって畑を耕すシーンが出てきます。(とにかくこの34巻は土とか泥とかのシーンがやたら多い) 耕しては雨で崩れて耕して、それだけのシーンがしばらく続く。頭や目で読むというよりも身体で読んでいるような感覚になりました。
井上さんは「SWITCH」のインタビューで物語にはあまり興味がない、と言っています。スラムダンクでさえ、ただいい試合を描きたい、いいプレイを描きたい、みたいなことを仰ってました。宮本武蔵、という人の在り方を描きたい、物語というよりは詩に近いと思う、と。ほとんど即興に近い感覚で描いているんだろうな、と僕は思いました。
モードジャズみたいだ、と思ったのです。基本の筋(物語)はあるけれど、ちゃんとそこへ戻ってくるならどこへ行っても、自由にやってもいいよ、みたいな。「絵」にこだわっているのは一目瞭然だし、本人も公言しておられるから、ストーリーやセリフよりもまず「絵」が飛び込んでくる。セリフを目で追うよりも「絵」を一枚一枚めくっているような感覚になるのでどうしても音楽のように身体的なリズムが出てくる。だから僕はわくわくしているのだと思います。「絵」だけはもう自由に本当に楽しそうに描いている。その楽しさが伝わるから余計わくわくする。同時に「命」を扱う漫画なので更にずっしりと心に響く。巌流島まで描くのか、いつ終わるか分からないけれど、重石のように心に残る作品になりそうです。
僕はガチガチのジャンプ世代ですが、井上雄彦さんと荒木飛呂彦さんだけは小学校から今でもコミックを楽しみにしています。
2012.11.05
村上龍 / 限りなく透明に近いブルー
buy viagra in brisbane
An generic cialis!小説を読むことの面白さを知ったのは何の本だったかと考えていたらこの本に行き着いた。
初めて読んだのは高1か高2だったと思う。
中学の終わり頃からだんだん読書が好きになっていった。最初は母親の影響で「三銃士」とか「ロビンソン・クルーソー」とか「ジュラシック・パーク」とか「フォレスト・ガンプ」なんかを読んでいたと思う。家にあったものを適当に読んでいた。
高校は全く面白くなくて授業中は小説か漫画ばかり読んでいた。当然の成り行きと言うべきか、村上春樹に出会い、村上龍に出会う。辻仁成なんかも良く読んでいた。「ノルウェイの森」は大好きな小説だったし、今では村上春樹は僕にとっても特別な作家だけれど、本当の意味で小説の面白さ、読書の喜びを教えてくれたのは村上龍だったと思う。「コインロッカーベイビーズ」「海の向こうで戦争が始まる」「ポップアートのある部屋」「トパーズ」「村上龍料理小説集」etc
その中でも「限りなく透明に近いブルー」がたまらなく好きだった。
破滅的な登場人物たち、過激な性描写、ドラッグ、ドアーズにストーンズ、ストーリーよりもその詩的イメージに僕は魅了された。村上龍はいつも怒りながら優しい文章を書いている。その文体は多くの人が認めるように天才的と言っていい。「現存する作家の中では、文章に関しては最大の天才と言えるでしょう」と高橋源一郎はある著作の中で言っている。僕もそう思う。きっと凄いスピードで文章を書くんだろうなと思う。
それはさておき、毎晩適当にページを開いて読んでは眠る日々があった。20代になってからもあった。いつも主人公がリリーに話しかける様子を見ていた。それはいつも限りなくイノセントなイメージを僕に与えてくれた。自伝的小説とは言え、著者があとがきで女の子に手紙を書いているのも何故かセンチメンタリズムを軽く通り越しているようでかっこよかった。
そんなわけで今でも膨大な量の書籍を出し続けているけれど、新作の小説が出るとわくわくする。
2012.10.01
内田樹 / 街場の文体論
この本を読んで泣いた、という人がいて僕はまさか、と思っていました。
この本を読み終えるまでは。
文体論の本で、「クリエイティブ・ライティング」と呼ばれる授業をまとめた本で、何故涙を流すのか。まさか、と思っていました。
しかし僕は泣いたのです。この本の最後の授業は「リーダビリティと地下室」というテーマで最後の項は「言葉の魂からくるもの」というものでした。ここでは村上春樹のエルサレム賞受賞スピーチが引用されていました。村上春樹の熱心な読書ならお分かりでしょうがここで引用されているのは有名な「卵と壁」の部分ではなく彼の死んだ父親の話です。僕も著者と同じように驚きました。村上春樹が家族、しかも父親について話すことは極めて稀だったからです。ここではとても書き切れませんが、父親は徴兵され中国へ送られた。前後生まれた村上春樹は毎日仏壇の前で手を合わせ祈る父親へ尋ねます。「なぜ祈るのかと」「戦場で死んだ人々のために祈っているのだ」と父は息子に教えます。そして父は息子の知らない記憶を持ち去っていく。
この本を読み終える日の朝、たまたま、本当に偶然に、村上春樹が朝日新聞へ中国との領土問題について寄稿した。文化交流に影響を及ぼす事を憂い、「国境を超えて魂が行き来する道筋を塞いではならない」と書いています。
村上春樹と文体論にどういう関係があるの?と聞かないでください。
ただ、僕はこの時「言葉の魂からくるもの」というのを「理解」しました。この本を読んでから、もう一度朝日新聞を読んだ時、著者の言う「届く言葉=言葉を届かせたいという熱意」「襟首をつかまれて、頼む、わかれ、わかってくれ」と身体をがたがた揺さぶられるような感じ、というのが理解出来た。著者の言うように脳ではなく、皮膚で理解出来た。
著者は言う『僕らの身体の中にあって、言葉や思想を紡いでいく基本にあるものはかたちあるものではない。~言葉というのは、「言葉にならないもの」を言わば母胎として生成してくる。それをソウルと言ってもいい』
そのような言葉だけが他者に届く。
魂の継承を理解し、著者と村上春樹の言葉が「届いた」から僕は泣いたのだと思います。
言葉を届けることは本当に難しい。でもこの本を読んでまた少し言葉について理解出来ました。他にも教育、子育て(子どもを育てることを損得勘定で考えてしまう社会)、お金について言及しています。著者の本はとにかく読み易い。難しい単語も幾つも出てきますが、それでもぐいぐい読ませる。何かモヤモヤして生きづらい社会だなと思っていたら少しスッキリするかも知れません。
copyright © blackbird books all rights reserveds.