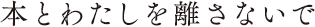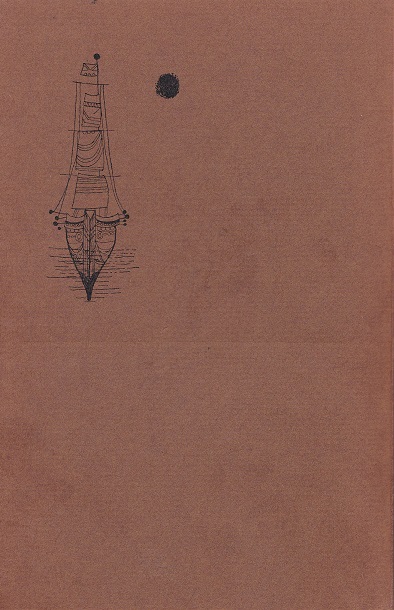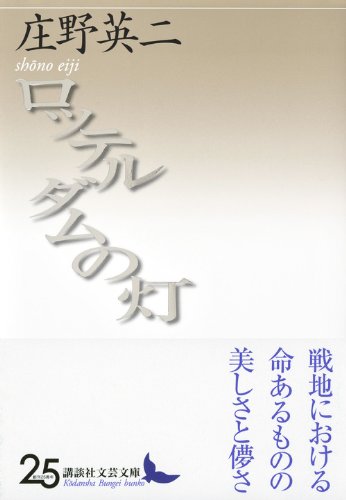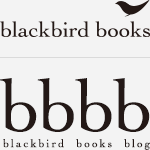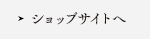2017.08.09ブログ
ロッテルダムの灯 / 庄野英二
あるお店の方にオススメして頂いた「ロッテルダムの灯/庄野英二」が大変面白かった。
弟の庄野潤三が好きでこれまでよく読んで来たけれど、恥ずかしながら庄野英二は読んだことがなかった。
「ロッテルダムの灯」は日中戦争、太平洋戦争を戦場で過ごした本人によるエッセイで、まえがきには「風にささいやいたものにすぎない」と記している。
戦争を題材にした小説のように劇的なドラマや修羅場が出てくるわけではない。
また、大変な苦しい思いをした、という痛切な出来事を語るわけでもない。
ただ現地で本人が見たもの、そして出会った人々についてありのままに語っている。
そこには敵や味方ではなく人間同士の交流が描かれている。
そして、とにかく花の名前をタイトルにした作品がたくさん出て来る。
そばの花、相思樹、うつぼかずら、マリーゴールド、カーネーション、椿、菜の花、サンパギータ、菊、カトレア、そしてバラ。
兵舎のあった豊橋、中国大陸、マレー半島、インドネシア、、それらの国々で見た花。
美しい花の思い出ばかりではないけれど、(そこには怒りや哀しみもあるが庄野さんはそれを軸には書いていない)
戦地にあっては悲惨な日常をふっと忘れせさてくれるものとして植物のその姿、香りが強く印象に残っていたのかも知れない。
それらの花にまつわる出来事が淡々と静物画のように綺麗な文体で描かれていて、戦時中の事とは思えない。
けれど、僕が戦時中の出来事の何を知っているというのだろう。
こういった本に出会う度に僕は何も知らないのだ、と痛感する。
「母のこと」という作品に中国で敵の一団に突撃するシーンがある。
敵の機関銃が雨あられと降ってくる中で突撃していく二十歳を過ぎたばかりの庄野青年は右肘に銃弾が命中し、
「生まれてから一度も経験したこともない、力とスピードと焼きただれるようなものが一緒になった強力な衝撃を受けて私の運動が停止させられてしまった」と書いている。
その時やられたと同時に頭をよぎったのは「母に叱られる」という観念だったらしい。いたずらを見つかった子どものような。
そしてその戦場でまわりの兵が戦死していくなか、庄野青年は日本へ搬送される。病院を見舞う母はもちろん叱るのではなく自分に責任を感じ「ごめんよ、かんにんしてよ」としきりに謝ったそうだ。
この本でほとんど唯一と言っていいほど臨場感のあるシーンだけれど、一つの真理が書かれているようで僕はまた自分の無知を恥じ、この本を何度も読み返そうと思うのだ。
※僕が買ったのは(ほとんど譲って頂いた)理論社の古い本ですが講談社文芸文庫からも出ています。
copyright © blackbird books all rights reserveds.