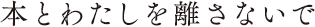2017.03.01ブログ
本と映画と痛み
紙を扱う仕事をしているので、手を切ることがある。
ページをめくるとき、ポスター、フライヤーを手に取るとき、段ボールから本を取り出すとき、しまうとき。
スッと切れて気づくときもあれば、帰宅後風呂に入ってヒリッとして気づくこともある。
これは肉体的な痛みだ。
本を読んでいるとき、あるいは映画を観ているとき、痛みを伴うことがある。
ここから先はもう読めない、この場面はもう観られない、そう思いながら目を逸らすことが出来ない。
場合によっては過去の出来事や現在抱えている悩みを思い起こさせ、胸が締め付けられることがある。
そこでは少なからず精神的な苦痛を伴う。
それでも人は本を読むことを止められないし、画面から目を逸らすことが出来ない。
何故だろう。
宮崎駿の映画は繰り返しTVで放映される。多くの人があらすじを知っていても、もう一度見たい、と思わせる何かがあるのだろう。
主人公たちが家族や恋人を失い、血を流し、自然が破壊され、爆弾を落とされようとも、また生きていくことを僕たちは知っている。
映画を観ている僕たちは登場人物たちの痛みと希望を心のどこかで共有している。
作者が大変な苦痛を伴いながら創り上げていることを僕たちは想像出来る。
身体的な痛みは共有出来ないが、心の痛みは同じ形ではなくともどこかで繋がることがある。
本(芸術)はその繋がりを開くキーでありツールだ。
本を開き、その扉の向こうがどうなっているのかは分からない。暗闇を手探りで進むことになるかも知れない。
けれど本を開かなければ分からないことは確実にある。
少し前に4歳の娘を連れて映画を観に行った。
子どもが両親を探しに旅へ出る話だったけれど、娘はその主人公の苦労あるいは悲しみに耐えられず途中で泣き出して映画館を飛び出してしまった。
アニメとは言えまだ早かったのかと思った。一方で感受性が鋭く、一点の曇りもないことに感動した。目を逸らさずに最後まで見よう、とは言えなかった。
ある時期からか、僕は多くの物事から目を逸らして来たのかも知れない。成長していなかったのかも知れない。
それを認めることは苦痛だった。
copyright © blackbird books all rights reserveds.