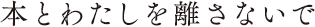2024.06.09ブログ
10年
かつて店の前には煉瓦造りのマンションが建っていて、そのエントランスには花壇があり、春になると黄色いモッコウバラを咲かせていた。古い煉瓦に黄色いバラはよく映えていた。店のカウンターからはそのバラがよく見えた。3年ほど前に、耐震性の問題だかでそのマンションは花壇ごと解体され、今は新しいマンションが建っている。バラがどうなったのかはわからない。
店を出てマンションに向かって左に折れるとすぐに交差点があり、右手には交番がある。交番の前を通り過ぎ、100mほど北に向かうと右手にスーパー、道を挟んだ向かいにファミリーマート。そして数m進むと緑地公園駅に出る。店から駅まで一直線、5分ほどだ。駅を通り過ぎてさらに進む。信号のない交差点。右手に駐車場、その向かいには駿台の予備校、交差点の角に弁当屋。その交差点からまた北に進む。この道は下り坂になっていて、歩道がかなり狭くなる割に交通量は多く、通る度に危ないなと思う。坂を下り切って、信号の手前の小道を右に曲がるとまた別の煉瓦造りの小さなマンションがあって、その3階の一室でblackbird booksは始まった。かなり古いマンションで(確か)入居者が減ってきたということで事務所や店舗に使ってもらおうとテナントを募集していたのだ。全てワンルームだった。当時1Fにあった器屋の「ミズタマ舎」さんに遊びに行ったら、そういうことを教えてもらって、条件などを聞いたら破格だったので、ほぼ即決した。
平日は他の仕事をしながらお金を貯め、週末だけその小さな部屋で細々と2年ほど営業して、今の場所へ移った。週末だけでもとにかく開業しないことには始まらないと考えていた。ワンルームの規模でやっていくつもりはなかったので元々他所へ移る前提で借りた。小さな部屋だったが自分の居場所を作れたようで誇らしい気持ちになったのを覚えている。
すでにオンラインショップを始めていたこと、屋号でSNSを使っていたこと、ビラ配りなどをしたこともあって、最初の何日かは意外なほど人が来てくれた。こんなわかりづらい場所まで階段を上ってやってくる人たちを見て、これはやっていけるのではないかと思ったのも束の間、客足はすぐに途絶えた。開業したのが6月で、梅雨の最中というのも大きかった。この年は毎週末が雨で街中が濡れていた。ミズタマ舎さんは1Fに出していたうちの看板が「濡れてるとこしか見たことない」と言い、ぼくは苦笑しながら内心はかなり焦っていた。梅雨が明けると間もなく真夏になり、駅からマンションへ数分歩いただけで汗が滝のように流れ、Tシャツと足取りを重くした。オンラインは動いていたし、本当に家賃は安かったので、売り上げがゼロの日があってもやっていくことは出来たが、店はお客さんが来ないと何も始まらないので、店を持てたことの喜びは徐々に消えていった。店をやる理由が見出せないのだった。
お盆を過ぎた頃からか、ある年配の女性が毎週顔を見せるようになった。50代後半から60代。小柄で地味な服装。30分ほど滞在し、一冊か二冊、必ず購入する。金額や冊数を問わず、定期的に扉を開け必ずお金を落としてくれるお客さんは神様と言っていい。その神様はどこから来ているのかわからなかったが、毎週来るということは恐らく近所なのだろう。その開業の年、夏の盛りから冬が静かにやって来るまでぼくは彼女のために店を開けた。彼女は暑い日も寒い日もどこからかやってきて、エレベーターのないマンションの階段を上り、どこの馬の骨かわからない無愛想な男が待っている古本屋の扉を開くのだ。彼女の中の何かを上手く捉えることが出来たのか、あるいは暇つぶしや散歩に丁度いいと思われたのか、どちらでも何でも構わない。とにかくぼくにとっては彼女が買ってくれることがやりがいとなった。そして週末だけとは言え一日でも店を休むことは彼女の大切な時間を奪ってしまうことになるのではないかと思った。彼女のために店を開けたい。彼女の歩いてくる道の先にぼくの店があり、その道筋から逸れないことが、お店を軌道に乗せることだと考えた。お店を続けるに当たって、目標、目的、願望など色々あるがぼくはまず見通しが欲しかった。この店に本を買いに来てくれる人がいること、品揃えは間違っていないこと。彼女が扉を開けることはその見通しをほんの僅かだが少しずつ確固たるものにしてくれた。数ヶ月して、当時まだ使っていたFacebookにとてもいい本屋だ、近所にこんな本屋が出来て嬉しいと彼女がコメントをくれた。神様はやはり近くに暮らしていたのだ。
長い冬が終わり、緑地公園の木々が涼しげな緑色に変わる頃、神様の来店が段々と減り始めた。毎週が隔週になり、隔週が月一になり、また梅雨が巡って来る頃には足が途絶えた。一周年の頃には常連と呼んでいい人たちも少しずつ出来て、本が売れないわけではないのだと自信を深め、そろそろもう少し広い場所へ移ろうと考え始めていた。どれくらいの家賃で、どれくらいの冊数を揃え、どれくらいの売り上げが一日あればやっていけるか。そんな見通しが立ち始めた。しかし彼女が顔を見せなくなったことが気に掛かっていた。
その梅雨の日も雨が降っていた。彼女から店に電話が掛かってきた。電話なんて初めてだ。申し訳ないが足を運ぶことが出来なくなったので今から言う本を宅配してくれないかとのことだった。ぼくは快諾し、店を閉めた後に彼女の家に向かった。彼女の家は駅とスーパーの並びにあるマンションの一室だった。エレベーターで彼女の部屋に向かい、呼び鈴を押す。家族であろう男の人が出てちょっと待ってくださいと言った。しばらく扉の前で待っていると彼女が出てきた。彼女はいつの間にか痩せ細り、弱々しく微笑んで用意していた代金をぼくに渡した。そのお金を持つ手はぼくがいつも見ていた手ではなかった。ぼくは状況を瞬時に理解し、本を手渡しながら「ありがとうございます。いつでも配達するので言ってください」とほとんど早口で、けれど大きな声で言った。彼女は「ありがとう」と微笑んで扉を閉めた。それが彼女との最後になった。
嫌な予感が的中したことにぼくは動揺し、何をどうすることも出来ないことに憤り、彼女が足を運んでくれた時間と日々を振り返った。また電話の掛かってくることを期待したのは束の間で、数週間後に亡くなったことをFacebookで知った。それからしばらくして良い物件が見つかり、今の場所へ店を移した。
今の店を彼女は知らない。あの見事なモッコウバラを見たこともない。10年経った今も毎日彼女の住んでいたマンションの前を通る。その道を通って店を開け、店を閉めるとその道を通って駅に向かう。毎日彼女のことを考えるわけではない。ただこうして振り返る時には彼女のことを思い出さずにはいられない。彼女がいなければぼくは早々に挫けていたかもしれないのだ。彼女の最後の「ありがとう」という声に耳を傾け、これからも店を開けるのだろう。
copyright © blackbird books all rights reserveds.