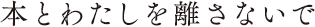2024.03.24ブログ
『もう一度猫と暮らしたい / 見汐麻衣』 さようならを伝える本

およそ10年ぶりに会う著者の夫が読んで欲しいと本を携えて東京からやって来た。
彼が立ち上げたレーベルから出すという。著者はシンガーソングライターで、一度彼女のライブを見たことはあったがその時は別のアーティストが目的だったこともあり正直に言うと歌も声も覚えていなかった。
レジで本を受け取った。上製のしっかりとした本だった。
どういう経緯かは知らないが装画は横山雄で帯文は小泉今日子。
見た目はいい本だと口には出さず胸の内で思い、特に内容の話はせず彼は買い物をして帰って行った。
本は物だからデザインが良い本であればすぐに扉を開いてみたくなる。
そのまま店で流し読みをして、家に帰り就寝前に精読した。
なぜ今まで本を出す(書く)ことがなかったのか、この文体はどこからやって来たのか、というのが最初の感想だった。それほどに比類出来る本も作家も見当たらなかった。
電車、喫煙所、台所(「お台所」の話が凄く良い)の風景、読んだ本や映画の話が幾つか続きエッセイの王道かと読み進めていくと次第に幼少の記憶を元にした文章が増えてくる。父親が家に帰って来なくなったこと、祖父母の家に預けられたこと、母の経営するスナックで歌を歌い小遣いを稼いだこと。この経験は多分に決定的で、9歳の頃から4年間、著者は店のカウンターで歌を歌った。スナックのカウンターだから、恐らくそのほとんどは歌謡曲だろう。そして松本隆ではなく、阿久悠の歌詞が文体に影響を与えていると思う。それから今に至るまで彼女は歌い手であり続けている。アーティストになりたいという夢があったのではなく、幼少の頃からそれは生活の糧であったわけだ。このバックボーンの強靭さが言葉の生い茂る幹のある文章を支えている。
幼少の頃の断片的な記憶を拾い上げながら「さかさまにゆかぬ年月よ」という紫式部の言葉を引用した手紙のようなエッセイからこの本は更に深みを増してくる。
「生き死に」とは、生まれた瞬間から誰の身の上にも等しく定められている事で始めから完結しているのだと思います。「死ぬまで生きる」と言う、永遠に回帰する時間の中にこの身を投げ出された瞬間から、自身の中にだけ在るものと捉えていた「命」は、他者との交わりが始まる事で、他者の中にも育まれ、関わり合い、支え合う都度、発酵していけるものだと思うようになっています。(「さかさまにゆかぬ年月よ」より)
タイトルになっている「もう一度猫と暮らしたい」はやはり幼少の頃の出来事が書かれている。祖母の「命は平等ではない」という言葉と「間引き」の経験が強烈で、当時6歳だった著者の記憶に深く刻まれることになった。
灯火のように揺れる命、そして現れては消える記憶に別れを告げる。もう戻らない時間を嘆いているわけではない。これは、本人の意図とは関わらず、「さようなら」を伝えるための本なのだ。
発売からずっと売れているから評判になっているだろうと思い、原稿の依頼がたくさん来ているのでは、と著者の夫に聞いてみた。来てるみたいだけどね、易々とは受けてないみたい。記憶を切り落とし、言葉を尽くして文章にするのだ。文章にするということは、本人の言葉を借りれば、その記憶を弔うということだ。簡単に手放すことはしないのだろう。その態度が文体にも現れている。
copyright © blackbird books all rights reserveds.