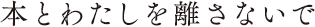2020.10.11ブログ
祖父を訪ねて
車があまりにも汚れていたので「洗車したら?」と父に言うと「誰も見てへん。乗れたらええねん」と返ってきた。
数年前に買い換えたというトヨタのヴィッツはフロントガラスも水色のボディも雨水や埃で黒ずんでいた。
父と二人で車に乗るのは何年ぶりだろうか。思い出せない。10年?20年?
ウイルスが他人事ではなくなってきた頃、98歳の祖父がデイサービス先で転んで腰の骨を折って寝たきりになり、数日入院した末に介護付き老人ホームへ移って行った。認知症ではなかったが元々目が悪い上に足元も覚束なくなってきたので転んだことには誰も驚かなった。記憶も曖昧で顔を合わすと「何処に住んどる?子どもの名前は?仕事は何しとる?」と毎回同じことを聞かれる。時々叔父(父の弟)と間違われる。
梅雨が明けた頃に見舞いに行こうとしたが「こういう状況なので予約制になり対面での面会は出来ない」と言われ足が遠のき、何となく夏が終わるのを待ってから予約をしてもらい、実家へ帰った。午前と午後、ひと組ずつしか面会は出来ないらしい。面会と言ってもオンラインで、ただでさえ会話の噛み合わない人と空間を挟んで上手く会話出来るのだろうか。祖父の状況を聞くと「目がほとんど見えなくなっている。食欲はあるし酒も飲むが流石に痩せてきた。でもはっきり喋るけどね」と母は言った。
朝食を済ませ、車に缶チューハイのケースと秋冬用の着替えを積んで父の運転で老人ホームへ向かった。「この街も汚くなってしまった」と父のぼやきを聞いていると10分強で着いた。
エントランスを抜けると左手に受付があって、女性のスタッフが「こんにちは」と元気に出てきた。父は慣れたように「お世話になっております」と荷物を渡し、そのまま広いロビーに向かい腰を下ろした。四人がけの木製のテーブルが三つ並んでいる。僕らの他には誰もいなかった。他のスタッフがどこからか出てきて「準備致します」と軽い足取りで廊下の奥へ消えていった。ロビーは庭に面していて東向きの窓から登り始めた陽の光を吸い込んでいた。窓の向かいには白い本棚がある。中井久夫の本が数冊と司馬遼太郎や津本陽の小説、それとオキーフの自伝が並んでいた。
本を読むでもなく背表紙を撫でていると「お待たせしました」と後ろから声がした。スマホを持ったスタッフが父の元へ歩み寄る。僕はてっきりモニター越しにどこか仕切られた空間で話すと思っていたので面食らった。この広い空間で手のひらに乗った長方形に向かって話すのか。スマホを覗くと鼻にチューブを差した祖父が仰向けに寝転んでいる。目は開いているのか閉じているのかわからない。祖父の傍でスマホを持っているスタッフの手が見え隠れしている。画面が顔に近づいていく。父が「もしもし」と声を上げると「—か?ご苦労さんです」と祖父が答える。僕の来ていることを父が伝えると「元気でやれよ、何処に住んどるんやった?子どもは元気か?仕事は何しよるんや」といつもと同じ会話が始まった。僕がどこで話をしようと祖父にはほとんど関係のないことだった。確かに痩せたように見えたが悲壮感はなかった。もうすぐ100歳なのだ。今更祖父のどんな姿を見てもさほど驚かない。ご飯を食べられて好きな酒を飲めるのだから十分だと思った。
形だけの面会はすぐに終わった。また来るよと通話を切った。いつ逝ってしまうかわからないが、せめてまた手を握れるように願うしかない。それよりも僕は帰り道、フロントガラスの汚れを見たときに父の「乗れたらええねん」という声がこだまして、言いようのない寂しさに襲われた。父は身だしなみに気をつける人だった。派手ではないが傷まない永く着れる上質の服を好んだ。服装や髪型について昔はとやかく言われた。みっともない仕草や装いを嫌った。外見と車のことは別の問題かも知れないが数年前までの父なら車をきちんと洗っていただろう。祖父はもうすぐ100で父は70、僕は40だ。これまで意識をしてこなかった30年の隔たりが僕の人生に影のように気配を消しながらぴったりと付いて来ていたことを知った。そしてその時間の重みやその重みがもたらすものが陽炎のような輪郭を持って目の前に迫って来ることを受け入れるしかなかった。
copyright © blackbird books all rights reserveds.